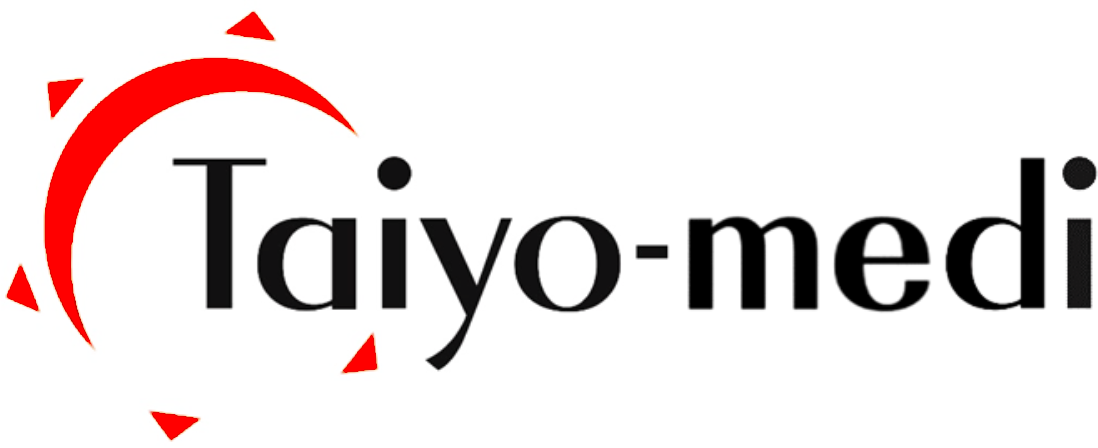太陽化学 メディケアグループ
医療・介護従事者向けサイト
医療・介護現場レポート
〜おひさま通信〜

排便ケアにおける皮膚・排泄ケア認定看護師の役割
釧路赤十字病院 様
釧路赤十字病院は、標榜科は19科、病床数は489床で、平成27年2月より54床の地域包括ケア病棟を導入し、現在は一般377床(NICU9床)、地域包括ケア病棟54床、精神58床となっています。
小児救急、周産期医療の拠点病院で、内科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、皮膚科、口腔外科、麻酔科の診療科があります。地域包括ケア病棟、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションがあり、在宅復帰支援にも力を入れて取り組んでいます。
さまざまな疾患が原因で、排泄に課題を抱える患者さんがいる中で、皮膚・排泄ケア認定看護師の役割も多岐に渡ります。今回は認定看護師としてご活躍中の平塚様にお話をいただきました。
排便コントロールが必要な患者さんについて
私が排泄に関わる患者さんは、外来では
1.ストーマ(人工肛門)造設している方(以下オストメイト)⇒化学療法・既往に糖尿病がある方もいます。
2.薬剤を使用してもコントロールできない便秘・下痢の方
入院中の患者さんでは、病棟の看護師から相談を受け
①褥瘡のある方
②疾患・薬剤による排泄障害(便秘・下痢)のある方
③活動量の低下・食事摂取量の低下等で便秘を引き起こしている方
④下痢をして皮膚トラブルが生じた方
へ介入して排便コントロールをおこなっております。
釧路赤十字病院における皮膚・排泄ケア認定看護師の役割
皮膚排泄ケア認定看護師は、創傷・オストミー(人工肛門・人工膀胱・瘻孔)・失禁の看護分野において看護実践を行う役割があります。
院内では、皮膚排泄ケア領域の依頼・相談を受け、実践ならびに指導を行っています。
入院している患者さんに対しては、医療スタッフからの相談を受け実践を通してスタッフ指導を行っています。
また、多職種と連携をすることで、患者さんが早期回復を図れるようにチームの一員として活動を行っています。外来では、患者さんが自宅で安心して生活が送れるように看護実践を行っています。

皮膚・排泄ケア認定看護師
看護師 平塚仁美様
オストメイトの方の排便コントロール~高発酵性食物繊維の活用~
オストメイトの方が安心して生活するためには、ストーマ装具が安定して貼れる必要があります。
そのため、ご本人にあった装具を選択し、大腸ストーマの場合はできるだけ有形便に整えたいと考えています。
便が柔らかい方には、食事摂取内容・下剤使用の有無等を確認して、必要な方には水溶性食物繊維のサプリメント(グアー豆由来の高発酵性水溶性食物繊維:以下PHGGと称す)を紹介しています。
患者さんへの説明は「善玉菌(ヨーグルト、発酵食品等)と一緒に、善玉菌の餌になる高発酵性食物繊維を摂ることで腸内環境が整い、形のある便に整え、ガスの量が減ることが期待できます。摂取をやめてしまうと腸内環境も少しずつ元の状況に戻ってしまうので、可能であれば続けてもらうほうが良いです。」と伝え、PHGG5g~10g/日とヨーグルト等を一緒に摂取することを勧めています。紹介したオストメイトの方からは、「これを飲んでから便の臭いが減った」「ガスが減った」「形がある便が出るようになった」と喜ばれています。

【左】 売店では患者さんに指導で紹介するものを取り扱っている
【右】 CST委員会の様子
頑固な便秘の方へ
頑固な便秘の方には、腸管の閉塞する病気がないこと主治医に確認しイヌリン配合のPHGGを紹介します。始める時は、10g~15g/日から開始しています。
4週程度で便秘が少しずつ解消する方が多く、排泄状況を確認しながら下剤量の調整をして適正な量の検討をしています。
下痢の方へ
下痢の方は、臀部の皮膚がただれることで相談を受けることが多いです。
臀部のただれは、ただれのケアをするだけでは根本的な解決にならないので、排便を有形に整える必要があります。
そこで薬剤や食事を調整しても改善しない下痢の方には、PHGGを5g~10g/日を使用してもらい腸内環境を整えます。
4週間程度で下痢だった排便が有形便に変わることが多く、排便回数も減ることで皮膚トラブルが解消していくケースが多いと思います。
疾患・薬剤・低栄養・消化吸収能力の低下等、腸内環境が悪化して下痢をしている方は薬剤だけでは腸内環境を整えるのは難しいことが多いです。そのため、下痢が持続している方には、腸内環境を整えて排便を有形便にするためにもPHGGを紹介しています。
糖尿病の既往のある方へ
糖尿病の既往のある方には、「毎食毎にPHGG3gずつ摂取することで血糖値の上昇を抑える効果が期待できおなかの調子も整えます」とお伝えしています。
当院では、便秘や下痢の方に水溶性食物繊維(PHGG等)やその他必要なものをご紹介する時には、すぐに使用が出来るように売店で販売してもらっています。
継続する方には、近隣のドラッグストアや販売店を紹介し、続けて摂取できるように関わっています。
食事面や生活面でのアドバイス
病院の食事は、食物繊維が18g/日入っています。
そのため、便秘の患者さんと関わる時には、食物繊維がどの程度摂取できているか確認しています。
摂取量が少ない場合には、NST(栄養サポートチーム)と相談し、食事摂取量が増えるように多職種で介入を行っています。
生活面では、看護師ができる排泄の援助をしています。朝の飲水で腸を動かし、胃結腸反射を利用して朝食後のトイレ誘導、腹部マッサージ・散歩によって腸蠕動を促す等、薬に頼らずにできる排泄ケアを取り入れています。
院内での活動~排泄委員会について~
CST(continence support team)は、排泄ケアを通して患者様の尊厳を守ることを目的に、昨年1月から開始となりました。
昨年はTENA社のオムツを導入して、オムツによる排泄ケアが必要な患者さんに正しく、快適に使用できるよう取り組みを行いました。
今年は2年目になり、10名の委員が2つのグループに分かれて取り組みを行っています。
1つ目のグループは、患者さんの排泄アセスメントを行い、排泄障害の予防・排泄障害のケアに関する介入を早期に行うための検討をしています。
2つ目のグループは、入院中だけではなく、退院した後も快適な排泄が継続されるように検討しています。排泄は毎日行う行為で、排泄に問題が起きると本人だけではなく、家族(介護者)の生活にも大きな影響を及ぼします。
とはいえ、排泄はプライベートなことで問題になりにくく、本人・家族だけで悩みを抱えていることも多いです。そのため、今年度の取り組みを行うことで、排泄障害に悩む方が一人でも少なくなることを目指してチームで活動を続けています。
ページの先頭へ